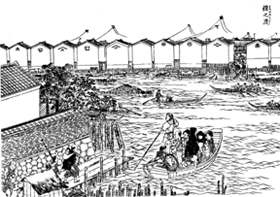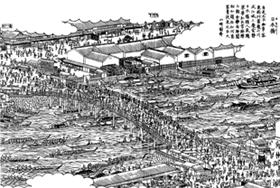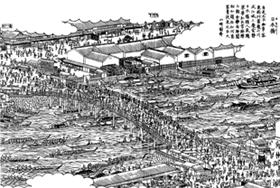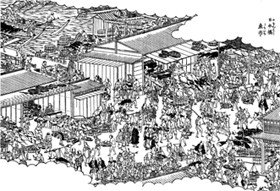|
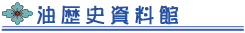
日本橋小網町今昔(1)
|
島商株式会社
代表取締役会長
島田 孝克
|
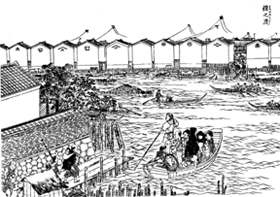
江戸名所図会より引用 鎧之渡 江戸時代から大正の大震災まで、日本橋川沿いの河岸には白壁の土蔵が立ち並び、美しい景観が見られました。俗に“小網町河岸三十六蔵”といわれ、広重の江戸名所百景のうち、“鎧の渡し小網町”に描かれています。その景観について、永井荷風は「日和(ひより)下駄」(講談社文芸文庫)に「私はかかる風景の中日本橋を背にして江戸橋の上より菱形をなした広い水の片側には荒布(あらめ)橋につづいて思案橋、片側には鎧(よろい)橋を見る眺望をば、その沿岸の商家倉庫並び橋頭の繁華雑踏と合わせて、東京市中の掘割の中にて最も偉大なる壮観を呈する処となす」と書いています。
荷風が大正3年の夏からおよそ一年にわたる東京市中散歩の記事をまとめた隋筆集ですから、関東大震災(大正12年)で白壁の土蔵が崩れるまでは、広重が描いたような風景であったのでしょう。
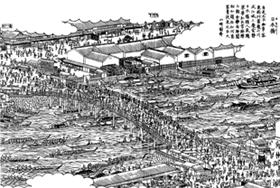
江戸名所図会より引用 「日本橋」 天下の城下町江戸の建設は、家康の江戸入り後、秀忠・家光・家綱の四代、70年にわたるものでした。
慶長8年(1603)、家康が二万石以上の大名に命じて、千石につき十人の人夫(千石夫)を集め、神田山を崩し、水路を埋め残し、豊島洲崎(現在の浜町から新橋辺り)を埋め立てて市街地の造成をしました。更に、江戸城普請の一環として日比谷の入江に直接流れ込んでいた平川を道三堀(現在の呉服橋から大手門に至る辺り)に繋ぎ換え、このうち、道三堀の西半分と外濠が埋め立てられて、残った水路が現在の日本橋川となりました。
荒布橋と思案橋(戦後は小網橋)はもはや残っていませんが、かっては渡し船が行き来していた“鎧の渡し”(俗に一文渡)は、明治5年に木橋が架けられ、明治21年に鉄橋となって今日に残ります。
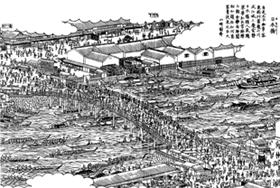
日本橋小舟町岸 左手「江戸橋」正面奥「荒布橋」
明治5年頃 野田宇太郎は「東京文学散歩・下町」(小山書店)のなかで、荒布橋のあった場所にたたずみ、明治の情景を回想しています。「ここに立つと右に江戸橋が架かり、左のぐっと弓なりに曲がった下流には鎧橋が見える。明治21年架橋のアーチ型の鎧橋の影はすでに五年前に失われてしまって、今は新しい鎧橋となっているが、濁った水の流れだけを眺めていると、やはりなつかしい過去の時代の思い出が漂っているようである。
水の都!という言葉が私の心に浮かぶのは、この荒布橋跡やもう一つ川下の東堀留川の入り口に架かっていた思案橋跡の水際に佇むときである。(中略)実際この辺りの水系は、江戸時代からの人々が愛して来た豊かな情調は大切に保存しながら、ヴェネチアあたりの水の都の特色を採り入れて、明治時代の良識ある都市計画者が慎重に設計した場所でもあった。」
思案橋の名称については「昔時遊客が、吉原に遊ばんか、堺町に往かんかと思案せし處なればこの名あり」(日本橋区史)と書かれていますが、親爺がこの橋まで来て、さて今日は吉原に行こうか、それとも芝居でも見ようかと“思案した”ので付けられたとも聞いています。ついでに、思案橋に続く堀留に「親父橋」がありました。
吉原を開いた庄司甚右衛門が架けた橋で、”親父”と呼ばれて親しまれてたので、親父橋と命名されたと言われます。(池田弥三郎「日本橋私記」)。
人形町界隈には元和3年(1617)に幕府公認の遊郭と芝居町が設定されました。
この辺りは葦(よし)や茅(かや)の生い茂る沼地で、当初は「葦原」といいましたが、後にめでたい文字をあて「吉原」としたようです。
吉原遊郭は明暦の大火を期に浅草日本堤に移転しましましたが、芝居町には歌舞伎小屋の「中村座」「市村座」や浄瑠璃の「薩摩座」、人形芝居の「結城座」などがありました。
江戸末期には、ほかに娯楽が少なかったので、「一町内一席」と言われたほどの「寄席」があり、大正5年の調べによると、日本橋区内に14ヶ所あったことが記録されています。
江戸城が築城された慶長・寛永の頃、小網町は江戸湊の内港であり、日本橋川の「河口洲」の小さな中島にすぎませんでした。江戸城にもっとも近接した浅草金龍山(浅草寺)下の大川から芝浦までの漁場は、小網町白魚役という漁民が御菜白魚上納を行う漁場として指定されていました。
慶長6年(1601)に家康が東金に鷹狩に出かける途上、小網町の漁師が網をひいて将軍の観覧に供したところ「肴(さかな)御用」を命ぜられ、白魚を献上する特権を与えられたといいます。
また、田中優子監修の「江戸の懐古」には「これより夜々十隻ばかりの船を出し、四ツ手網を用いて、小魚を取り、朝にいたれば、佃島に漕ぎ帰り、その途中、日本橋小網町二丁目なる思案橋の西詰めに網を干すを例とす」と書かれています。
小網町は、寛永年間(1624~1644)には“番匠(はんぢゃう)町”と称し、それ以前は”入江ケ岡”と呼ばれ、後に小網稲荷に因んで「小網町」と改めたようです。
小網稲荷神社は江戸七福神詣の一社で文正元年(1466)に創建され、太田道灌が崇敬したといわれます。堀のそばで舟にかかわりが深いところから、宝船の社(やしろ)として知られ、弁財天と福禄寿が祀られています。この辺りは大名旗本屋敷ばかりで、小網町二三丁目と安藤対馬守邸の間を「稲荷(とうかん)堀」と呼び、江戸の真中の地でありながら、白昼若き婦女子が一人で通行すると下郎などが戯れることがあるので、廻り道をするくらい淋しい土地であったようです。(鹿島萬兵衛「江戸の夕栄え」中央文庫)。
小網町一丁目を「末広河岸」、二丁目の思案橋側を「貝杓子店」又は日本橋川に沿った河岸を「鎧河岸」とも呼ばれていました。
江戸の初期には日本橋を中心に京橋、本所、深川地域に多数の川(堀)が縦横に廻らされ、水運によって各地の物資が河岸で陸揚げされました。享保期(1716~1736)以降になると、本船町、伊勢町、小網町、小舟町、八間町、堀留町、堀江町及び堀江六間町の八町には米問屋が集まって「河岸八町」と呼ばれていました。

江戸名所図会より引用 新川酒問屋 小網町河岸には川舟積問屋が目立って多く37件もあり、その大半は小網町二三丁目に集中しています。次に多いのが船宿で16軒もありました。塩、油、米、酒、醤油などの食品問屋は、川舟積問屋や船宿を兼業しているところが多く、日本橋川は猪牙(ちょき)船や茶船、荷足船(にたりぶね)などの伝馬船が多く出入りして賑わっていました。
江戸に到着した諸国の千石船(後に菱垣・樽廻船)は品川・佃島沖辺りに停泊し、そこで荷を茶舟に移して大川(隅田川)から日本橋川へと入り、桟橋から天秤で担いで蔵に運ばれました。
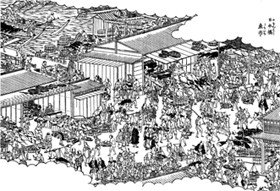
江戸名所図会より引用 日本橋魚市 日本橋から江戸橋までの北側(本船町、按針町、本小田原町)が、関東大震災後に築地に移転するまで、「魚河岸」でした。
日本橋といえば「一日に三千両のおちどころ」(川柳)、朝は魚河岸、昼は芝居町、夜は吉原と言われ、江戸の景況を左右するほど繁盛していました。
日本橋川は今日の流通センターのような役割を果たしていたと言えましょう。
江戸で消費される日用消費物資は繰綿(くりわた)・木綿・醤油・酒・油などの加工品が多く、主に上方(機内)から送られてくる“下り物”でしたが、米・炭・薪(まき)・味噌・魚油・塩などあまり技術を要さない商品は、江戸周辺や関東地域の“地廻り物”で維持されていました。
関東一帯の塩は、幕府の保護のもとに下総の行徳塩に依存していました。幕府は新川と小名木川を開削して、江戸と下総を結ぶ水運を開発し、寛永9年(1632)には行徳河岸(小網町三丁目)から行徳行きの定期便を運航させました。
これにより、武蔵国からは物資のみならず、商人や旅人が頻繁に往来するようになり、船宿が栄えました。行徳船は長渡船又は番船と呼ばれ、寛文元年(1671)には53隻、寛永年間(1848〜1853)にかけては62隻に増加しています。
その後、江戸の人口が増えるにつれて塩の需要が満たされなくなり、寛永末から瀬戸内産の十州塩が「塩廻船」によって江戸へ運ばれ、大川から南北新堀町河岸(今の箱崎辺り)の下り塩問屋に直送されるようになりました。
承応年間(1652〜1655)に江戸に入った塩廻船は250〜300艘、積載量約50万俵でしたが、明治初年には3万艘、積載総量210万俵に増えています。
この大量の塩を四軒の下り塩問屋(松本屋、渡辺屋、長嶋屋、秋田屋)が仕切り、21軒の仲買が配給していました(廣山尭道「塩の日本史」雄山閣出版)。
この下り塩問屋には醤油問屋を兼ねているものがあり、江戸入りの下り醤油が地廻りものになると、銚子から醤油を仕入れるようになり、空船に塩を積んで銚子へ帰すという「奥川筋船積問屋」が生まれました。
江戸という大消費地だけに、十組醤油酢問屋は多く、文政期には70軒もありました。こうして銚子と小網町との間に多様な物資の交流が始まり、銚子からは醤油のほか、大麦、味噌、酒粕が、小網町からは明樽、提灯、蝋燭、紙、筆、麻、白絹、酒、酢などの日用品が運ばれるようになりました。
(奥川筋とは武蔵・上野(こうずけ)・下野(しもつけ)・常陸(ひたち)・下総(しもうさ)などの内陸奥地の川を指します)小網町一丁目の思案橋側からは上総(かずさ)国登戸曾我野行きが、江戸橋土手からは木更津船が発着していました。
小網町河岸の光景を「このほか荒川上流、上州、武州行きの川船も皆小網町河岸白壁の土蔵数町の間軒を並べ、川にはこの多くの船々の荷積み荷卸しの光景を江戸橋、荒布橋上より眺めて、始めて江戸見物に来りし田舎人の目を驚かすは無理ならず。
当時江戸名所の一ツなりし」と鹿島萬兵衛が「江戸の夕栄」で述べています。
江戸時代の初期には、油も下り油が圧倒的でした。
万治3年(1660)に霊岸島に「油仲間寄合所」(東京油問屋市場の前身)が設立され、下り油の売買所が定められました。元禄7年(1694)には江戸十組問屋が組織され、水油問屋34名が河岸組として参加します。次いで享保11年(1726)には、地廻り水油問屋31名が加わるようになり、関東地廻りの油が次第に増えていきます。
天保2年(1831)には江戸の年間需要量10万〜11万樽のうち、地廻り油は30%を占めます。これには関東の綿作の発展や幕府による油菜作付けの奨励と菜種油の増産がありました。
こうして、江戸時代の小網町をみると、ここが下りものと関東地廻りものの接着点であると共に、関東各地への物資発船地でもあったことが分かります。
今では往時の面影はありませんが、小網町河岸が江戸湊の内港として重要な役割を果たしていたことが分かります。
参考文献:白石 孝「日本橋街並み商業史」慶応義塾大学出版会
白石 孝「日本橋街並み繁昌史」慶応義塾大学出版会
【油歴史資料館に戻る】 |